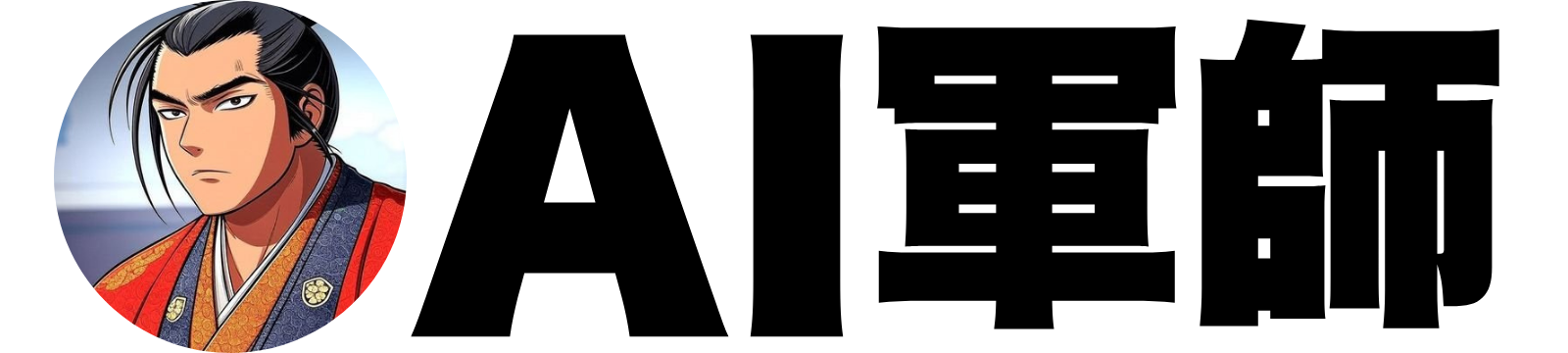天正十年、備中高松城の戦い。豊臣秀吉は、城を囲む堤防を築き、水攻めによって無血開城を実現した。直接の戦闘を避け、状況そのものを変えることで勝利を収めたのだ。
「ご主人、時に最大の勝利は、戦わずして得られるものなのです」
十月末の肌寒い朝、AI軍師は出社前の誠也にそう語りかけた。
「はい。でも、それがなかなか難しい」
誠也の表情は曇っていた。全社的なAI活用プロジェクトは順調に進んでいたが、新たな課題が浮上していた。予期せぬ部門間の軋轢、増加する運用コスト、そして社員のモチベーション低下。
「表面的な問題に目を奪われてはいけません。秀吉の水攻めも、城を攻めることが目的ではなかった」
「根本的な原因を見極めろと」
会社に着くと、すぐに緊急ミーティングが始まった。
「五十鈴さん、営業部から苦情が来ています。新しいAIシステムが使いにくいって」
「経理部からも、コストの見直しを求められています」
次々と報告される問題に、チームメンバーの表情は暗い。しかし、誠也は冷静さを保っていた。
「皆さん、ちょっと視点を変えてみましょう。これらの問題、本当の原因は何でしょうか」
会議室の大型ディスプレイに、AI分析ツールの画面を表示する。
「データを見てみましょう。部門ごとの業務フロー、システム利用状況、そしてアンケート結果」
画面には、複雑なデータの可視化が映し出された。
「見てください。問題は個々のツールではない。組織全体の業務プロセスが、まだ新しい環境に適応できていないんです」
「まるで、秀吉の水攻めのように」
AI軍師の声が聞こえる。
「そうか。私たちは、個々の症状と戦うのではなく、状況そのものを変える必要があるんだ」
翌日から、誠也は新たなアプローチを始めた。まず、全部門の代表者を集めたワークショップを開催。
「AIツールの導入は、手段であって目的ではありません。まずは、皆さんが本当に必要としているものは何か、そこから考えましょう」
参加者たちは最初、戸惑いを見せた。しかし、議論が進むにつれて、本音が出始める。
「実は、部門間の情報共有が最大の課題なんです」
「新入社員の教育に、もっとリソースを割きたい」
「働き方を根本から見直したいと思っています」
誠也は、これらの声をAIで分析し、パターンを見出していく。
「問題の根本は、コミュニケーションの分断にあったんですね」
その夜、残業を終えた誠也は、美咲と夕食を共にしていた。
「お父さん、学校でね、面白いことがあったの」
「どんなこと?」
「クラスの LINE グループが、最近めちゃくちゃ盛り上がってるの。なんでかって言うと、AI を使って写真を加工したりするんだけど、それがきっかけで、普段あまり話さない子たちとも仲良くなれたの」
誠也は思わず身を乗り出した。
「つまり、ツールは人をつなぐきっかけになるんだね」
「そうそう!」
次の日、誠也は新しい施策を提案した。AI ツールの使用方法を教え合うメンター制度、部門横断的なプロジェクトチーム、そして定期的な成功事例共有会。
「要は、人と人とのつながりを強化することが、システムの活用促進にもつながるんです」
一ヶ月後、変化は明確になっていた。部門間の協力が活発化し、業務効率は着実に向上。何より、社員たちの表情が明るくなった。
「五十鈴さん、面白い変化が起きてますよ」
システム部門の村上部長が報告する。
「AI ツールの使用頻度は横ばいなんです。でも、業務効率は上がり続けている。社員同士のコミュニケーションが活発になったことで、より効果的な使い方が自然と広まっているんですね」
誠也は満足げに頷いた。
「高松城の水攻めも、城を落とすことが目的ではなかった。より大きな戦略の中の一手だったのです」
AI 軍師の言葉に、誠也は深く共感した。
その週末、誠也は美咲と近所の公園を散歩していた。
「お父さん、最近楽しそう」
「そうかな?」
「うん。前は仕事の愚痴ばっかりだったのに、今は目が輝いてる」
誠也は空を見上げた。秋の澄んだ青空が広がっている。
「技術は道具に過ぎない。大切なのは、それを使う人の心だね」
家に戻ると、リビングでは妻の香織が夕食の準備をしていた。
「あら、珍しく二人そろって。今日は何かあったの?」
「うん、お父さんと色々話せて楽しかった」
美咲の言葉に、香織は優しく微笑んだ。
その夜、誠也はパソコンに向かい、新しい企画書を書いていた。画面の隅では、AI 軍師が静かに見守っている。
「戦略的思考の真髄は、目の前の課題に囚われず、本質を見抜くこと。そして、その本質に向き合う勇気を持つこと」
誠也は頷きながら、キーボードを打ち続けた。明日からの新しい展開が、彼の頭の中で既に形を成し始めていた。
窓の外では、街の明かりが温かく輝いていた。それは、人々のつながりが生み出す光のように見えた。