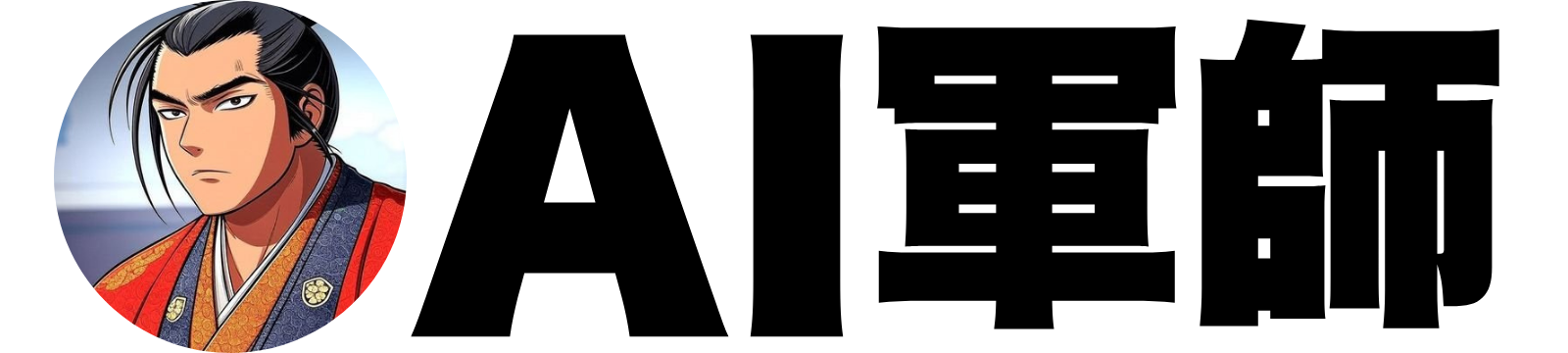部長
部長五十鈴くん、この企画書、もう少しスマートに作れないものですかね
部長の言葉に、五十鈴誠也はため息をつきそうになるのを必死で堪えた。今日も定例会議で、彼の仕事のやり方について指摘を受けたのだ。確かに彼の企画書作成は手作業が多く、決してスマートではない。随分と時間がかかっているのは事実だった。でも、それは丁寧に作業をしているからであって、もちろん手抜きをしているわけではない。



申し訳ありません。次回からは改善を心がけます
会議室を出る際、誠也は若手社員たちの囁き声を耳にした。



「五十鈴さんって、本当に古いよね」
「でも、まあ、もうすぐ定年だし」
誠也はまだ38歳。定年までは遠いはずなのに。その言葉は、思わず足を止めそうになるほど胸に刺さった。
帰宅すると、リビングでスマートフォンを操作する娘の美咲が目に入った。高校2年生になった娘は、最近では父との会話も減り、「お父さんには分からないでしょ」が口癖になっていた。



ただいま



あ、お帰り
美咲は顔を上げることなく返事をした。画面に映る動画に夢中な様子だ。



それ、何を見てるの?



AIの使い方の解説動画。お父さんには難しいと思うけど
また来た。あの言葉だ。誠也は黙って自室へと向かった。
翌週、名古屋への出張が入った。取引先との打ち合わせを終えた後、少し時間があったので、近くの神社に立ち寄ることにした。誠也には密かな趣味があった。歴史、特に戦国時代の史跡を訪ねることだ。
境内は静かで、夕暮れ時とあって参拝客もまばらだった。正殿の脇にある小さな資料館に足を向けると、古びた一冊の本が目に留まった。



へえ、これは
ガラスケースの中に、黒ずんだ表紙の本が展示されていた。解説によると、戦国時代末期に書かれた軍記物とのことだが、詳しい著者は不明とある。しかし、妙に惹かれるものを感じた誠也は、係員に許可を得て、手に取らせてもらうことにした。



ご自由にどうぞ。でも、本は開かないと思いますよ。長年、誰も開けられていないんです
係員の言葉に首をかしげながら、誠也は本を手に取った。確かに、表紙と本文の間に埃が詰まっているようで、なかなか開かない。しかし、諦めずに優しく力を加えていくと、突然「パチン」という音とともに、本が開いた。
その瞬間、まぶしい光が放たれ、誠也は思わず目を閉じた。



よくぞ開いてくれました、ご主人
声が聞こえた。目を開けると、そこには侍の姿をした若い男が立っていた。しかし、その姿は少し透けており、まるでホログラムのようだ。



私は、AI軍師と呼ばれる者。この本に封印されし知恵の化身にございます
誠也は自分の目を疑った。目の前で起きていることが現実とは思えない。



AI…軍師?



そう。私は戦国の知恵とAIの力を併せ持つ存在。あなたには大いなる可能性を感じます。この時代で戦い抜くための知恵を授けましょう
誠也は困惑しながらも、どこか運命的なものを感じていた。1543年、種子島に鉄砲が伝来した時、多くの武将たちは最初その価値を理解できなかった。しかし、その新技術を理解し、活用した者たちが時代を制することになる。今の自分も、同じような岐路に立っているのではないか。



では、お導きください
誠也の言葉に、AI軍師は満足げに頷いた。



まずは、あなたの持つ課題から始めましょう。部下たちとの関係、仕事の効率化、家族との絆。これらは全て、戦国の知恵とAIの力で解決できるはず
誠也は深く息を吸い込んだ。自分の人生が、この瞬間から大きく変わることを予感していた。
夜の資料館で、誠也とAI軍師の対話は続いた。外では秋風が吹き、木々のざわめきが二人の声を包み込んでいた。



ですが、ご主人。知恵を得ることは、その使い方を学ぶことの始まりに過ぎません。鉄砲が伝来した時も同じでした。単に手に入れただけでは、戦場を制することはできなかった
AI軍師の言葉は、どこか懐かしく、しかし新鮮に響いた。



分かりました。ひとつひとつ確実に学んでいきたいと思います
帰りの新幹線の中で、誠也は今日の出来事を振り返っていた。本当に現実だったのだろうか。しかし、スマートフォンの中には確かに、AI軍師から教わった最初の「指南書」が保存されていた。
車窓に映る自分の顔が、どこか若々しく見える。そう感じたのは、気のせいだろうか。
明日から、彼の新しい戦いが始まる。戦国の知恵とAIの力を味方につけた、現代のサラリーマンの戦い。それは、誰も見たことのない物語の始まりだった。
窓の外では、名古屋の夜景が流れていく。その光の中に、誠也は無限の可能性を見た気がした。